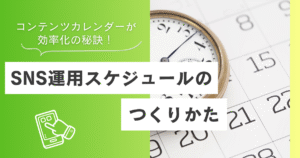《アイキャッチ画像を挿入》
- 社内でSNS運用のルールが決まっていない。どんなルールがいいの?
- SNS運用で炎上しないか不安…
- 担当者が辞めたら運用が止まってしまいそう…
こんな悩みにお答えします。
企業のSNS運用は、今や広報戦略に欠かせない要素です。しかし、運用の方法を誤ると、会社の評判を大きく損ねるリスクも…。
特に、企業アカウントは個人のアカウントとは異なり、社会的な影響力が大きいため、綿密なルール策定が不可欠です。
そこで、今回は以下の内容について、わかりやすく解説します。
- 企業のSNS運用にルールが必要な理由
- 企業のSNS運用ルール4種類とそれぞれの特徴
- 担当者必見!企業のSNS運用ルール10選
- SNS運用ルールを作成する4ステップ
- SNS運用ルールでは『見直し』・『更新』が肝心な理由
この記事を読めば、SNS運用におけるリスクを避け、効果的な運用体制を築くための具体的なルール策定方法がわかります。
ぜひ最後まで読んで、貴社のSNS運用をより安全で成果の出るものにしてくださいね。
企業のSNS運用にルールが必要な理由
どうしてSNS運用ではルールを設ける必要があるのかと言うと、それは企業にとって多くのメリットがあるからです。
ここでは、SNS運用にルールが必要な具体的な理由を5つご紹介します。
- 担当者への負担軽減
- 属人化の防止
- 目的と役割の明確化
- 炎上トラブルの防止
- クオリティの担保
納得感を持ってSNS運用のルールを決められますので、すべて確認しておきましょう。
担当者への負担軽減
SNSの運用では、以下のように多岐にわたる業務が発生します。
- 投稿内容の検討
- 投稿内容の作成
- 承認
- ユーザーとのコミュニケーション
- 投稿後の効果測定
担当者は日々これらの業務に追われ、精神的な負担を感じることもあるでしょう。明確なルールがなければ、何を発信して良いか、どのように対応すれば良いか、常に迷いが生じてしまいます。
しかし、ルールがあれば、担当者は迷うことなく業務を進められ、負担が軽減されます。
担当者は安心して業務に集中でき、より質の高いコンテンツ作成に時間を費やせるでしょう。
属人化の防止
属人化とは、特定の社員しか業務のやり方や状況を把握していない状態を指します。
SNS運用でルールを定めずに属人化が進むと、担当者が退職したり異動したりした場合に、運用が滞る可能性があります。そのため、投稿の基準や言葉遣いのルールなど、具体的な規定を明記することが重要です。
また、属人化は知識やスキルの共有を妨げ、組織にノウハウが蓄積されない原因にもなります。誰が運用を担当しても、一定の品質を保てるよう、あらかじめガイドラインを作成しておきましょう。
これにより、担当者の交代があってもスムーズに引き継ぎができ、安定したSNS運用を継続できます。
目的と役割の明確化
SNS運用を成功させるためには、運用する目的を明確にし、それぞれの担当者の役割をはっきりさせることが重要です。
ルールを設けることで、何のためにSNSを運用するのか、誰がどの業務を担当するのかが明確になります。
たとえば、顧客とのエンゲージメントを高めるという目的があれば、それに沿った投稿内容や返信の仕方をルールとして定めることができます。役割が明確になれば、各自が責任を持って業務に取り組め、効率的な運用が実現します。
また、目的が共有されることで、チーム全体の方向性が一致し、一貫性のある情報発信が可能となるでしょう。
炎上トラブルの防止
SNS運用において、炎上トラブルを未然に防ぐことは最も重要な目的の一つです。
なぜなら、SNSでの炎上は、企業のブランドイメージに深刻な影響を及ぼす可能性があるからです。
SNSは手軽にコミュニケーションが取れる一方で、トラブルに発展しやすいという側面があるため、その特性を十分に理解した上で運用することが不可欠です。炎上防止のためには、具体的なルールを定める必要があります。
たとえば、企業イメージにふさわしい言葉遣いの例や、不適切・差別的な表現を避ける旨を明記しましょう。また、政治や宗教、社会問題に関するデリケートな話題の取り扱い方についてもルールを設定しておきましょう。
万が一トラブルが発生したときの緊急対応の手順も明確にしておきましょう。即座の対応や責任者の設定、そして適切な声明の発信フローを定めておくことで、被害を最小限に抑えられるからです。
クオリティの担保
SNS運用におけるガイドラインは、社内の認識を統一し、投稿のクオリティを一定に保つうえで重要な役割を果たします。
特に、複数のスタッフがSNSアカウントを運用する場合、ユーザーに対して一貫したブランドイメージを伝えるためには、ガイドラインの存在は不可欠です。
たとえば、会社としてのブランドイメージを損なわないよう、以下の要素を明確にしておきましょう。
《以下の項目を図解して、イメージとして挿入》
- ブランドイメージ:どのような雰囲気を伝えるべきか
- ブランドのペルソナ:どのような層のユーザーに語りかけるか
- 投稿内容:どのような種類の情報を発信するか
- トーン&マナー:投稿の言葉遣いや雰囲気をどうするか
- 投稿頻度:どのくらいの頻度で投稿するか
- 推奨画角:写真や動画の最適なアングルは何か
- 参考写真例:具体的なイメージを共有するための見本
これらの要素を明確にすることで、誰が投稿しても会社の目指すブランドイメージを維持し、質の高いコンテンツを提供できるようになります。
結果として、ユーザーは一貫した情報に触れることができ、ブランドへの信頼感やエンゲージメントの向上が期待できます。
【4種類】企業のSNS運用ルールと特徴
企業のSNS運用に関するルールは、対象者や目的に応じて主に4つの種類に分けられます。
- 公式SNS運用ガイドライン(社内向け)
- ソーシャルメディアガイドライン(社員向け)
- ソーシャルメディアポリシー(社外向け)
- コミュニティガイドライン(ユーザー向け)
それぞれ異なる役割があるため、適切な使い分けが重要です。
これらのルールの特徴と目的について、順に見ていきましょう。
①公式SNS運用ガイドライン(社内向け)
公式SNS運用ガイドラインは主に社内のSNS運用担当者や関係者に向けて作成されます。
このガイドラインの目的は、企業として公式に運用するSNSアカウントの具体的な運用方針や手順を明確にすることです。
たとえば、以下のような項目が挙げられます。
- 投稿内容の承認プロセス
- 使用して良い画像や動画の基準
- ハッシュタグのルール
- コメントへの返信方針
これにより複数の担当者が関わる場合でも一貫性のある運用ができるため、誤情報の拡散や炎上リスクを低減できます。
また、担当者の業務負担を減らし、効率的な運用を促進する役割も担っています。
②ソーシャルメディアガイドライン(社員向け)
ソーシャルメディアガイドラインは、企業の全社員を対象としたルールです。
これは、社員が個人のSNSアカウントを使用する際に、企業の一員としてどのような点に注意すべきかを定めたルールです。
たとえば、以下のような内容が挙げられます。
- 会社の機密情報や顧客情報をSNS上で公開しないこと
- 会社の評判を損ねるような発言を避けること
- 個人の意見と会社の意見を混同しないこと
このガイドラインがあることで、社員一人ひとりがSNS利用に関する意識を高め、意図しない情報漏洩や炎上リスクの未然防止につながります。社員教育の一環としても非常に重要な位置付けとなります。
③ソーシャルメディアポリシー(社外向け)
ソーシャルメディアポリシーは、企業がSNS運用に関する基本的な考え方や姿勢を、社外に向けて公表するものです。
もちろん、企業にとってのステークホルダー(顧客、取引先、株主など)も含まれます。
企業がどのような目的でSNSを活用し、どのようなコンテンツを発信していくのか、またユーザーとのコミュニケーションにおいてどのような姿勢を取るのかを明確にするためのものです。
透明性を高め、企業の信頼性を向上させる目的があります。ウェブサイトなどに掲載されることが多く、企業のブランドイメージや倫理観を伝える重要なツールとなります。
④コミュニティガイドライン(ユーザー向け)
コミュニティガイドラインは、主に企業が運営するSNSのコミュニティやコメント欄などで、ユーザーに守ってほしいルールをまとめたものです。
このガイドラインは、健全なコミュニティ環境を維持し、ユーザーが安心して利用できる場を提供するために不可欠です。
なぜなら、誹謗中傷や勧誘行為、スパム行為など、モラルに関わる注意点を明記することで、問題のある投稿の未然防止に役立つからです。
また、コミュニティガイドラインに違反した場合の対処についても明記しておくことが重要です。
たとえば、投稿の削除やアカウントのブロック、フォローの中止など、具体的な措置を記載しておくことで、万が一の事態にも迅速に対応できるよう準備ができます。ユーザーが気持ちよくSNSを楽しめるよう、コミュニティ全体が自浄作用を持てるような働きかけを盛り込むこともおすすめです。
これにより、活発で建設的なコミュニケーションが促進され、企業とユーザー双方にとってより良い関係を築くことができます。
【必見】企業のSNS運用ルール10選
効果的なSNS運用を実現するためには、具体的な運用ルールを策定することが重要です。
ここでは、企業がSNS運用で考慮すべき10のルールをご紹介します。
《箇条書きの数が多いので、必要に応じてアイコン化するなどして図示してください》
- 基本方針や原則
- SNS運用体制
- 個人の責任範囲
- 機密情報の保護
- 投稿内容のトーン&マナー
- 信頼性や根拠のある情報発信
- 知的財産権の保護
- 誹謗中傷の禁止
- ステルスマーケティングの禁止
- ユーザーからの問い合わせ先
これらのルールを明確にすることで、トラブルを避け、安定した情報発信が可能になります。
それぞれの注意点も合わせて確認しましょう。
①基本方針や原則
SNS運用における基本方針や原則を定めることは、運用全体の土台となります。
まず、「なぜSNSを運用するのか?」という明確な目的を掲げましょう。
たとえば、以下のように具体的な目標を設定します。
- 「顧客との関係構築」
- 「ブランド認知度の向上」
- 「新商品の告知」
次に、「どのようにSNSを活用して企業の成長につなげるのか?」という活用方法を具体的に記載しましょう。SNSを運用する社員がどのような姿勢でSNSを取り扱い、向き合うべきか、基本的な考え方を明記することもおすすめします。
これにより、すべての担当者が共通の認識を持ち、一貫性のある情報発信が可能となります。より目的達成に向けた運用を進めやすくなるのです。
②SNS運用体制
企業アカウントのSNS投稿業務は、複数人で運用できる体制を整えておきましょう。
なぜなら、業務の属人化を防ぎ、担当者の異動や退職が必要になった場合でもスムーズな引き継ぎが可能になるからです。
また、投稿内容を複数人で確認すれば、誤字脱字や不適切な表現といったトラブルのリスクを減らせるだけでなく、担当者にかかる心理的な負担も軽減できるからです。
社内での対応に不安がある場合は、SNS運用の専門知識を持つ外部の業者に依頼することも一つの選択肢。プロに依頼することで、社内の負担を最小限に抑えつつ、より魅力的で効果的な情報発信につなげることができます。
③個人の責任範囲
SNS運用によってトラブルが発生した場合に備え、SNS担当者の責任がどの程度まで及ぶのかについて、あらかじめ明確に取り決めておきましょう。
社員個人の意見と企業全体の意見に関する認識も規定しておくと、予期せぬ事態が起こった際に役立つでしょう。
このような内容を明記しておくことで、社員一人ひとりが自分に課せられた責任を自覚し、より慎重で適切なSNS運用につながります。
責任範囲を明確にすることは、担当者の安心感にもつながり、日々の業務に集中できる環境を整えることにも貢献します。
④機密情報の保護
企業にとって機密情報の保護は非常に重要な課題です。
ご存知のように、企業活動には人事情報や事業戦略、顧客情報など、第三者に知られると企業の利益や競争力に影響を及ぼす可能性のある情報が数多く存在します。
これらの情報をSNS上で誤って漏洩させてしまうと、最悪の場合、企業の存続を脅かすほど深刻な問題を引き起こす可能性があります。そのため、どのような情報が機密にあたるのかを社員が正確に理解できるよう、社内でのトレーニングを徹底する必要があります。
機密情報の取り扱いに関する具体的なルールを設け、社員全員に周知徹底することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑え、企業の安全を守ることができます。
⑤投稿内容のトーン&マナー
SNS運用において、以下のようなコンテンツに関するルールも設定しておきましょう。
- 投稿内容
- 言葉遣い
- 投稿頻度
- 撮影場所や画角
- 文体(ですます調など)
ルールやニュアンスを伝えにくい場合は、参考となる具体的なアカウントを共有すれば、イメージのずれを防ぎやすくなります。
あらかじめトーンやマナーをきちんと決めて共有しておけば、SNS運用に対する社員の理解度は深まり、会社全体のブランドイメージを守りつつ、質の高いコンテンツを継続的に発信できるようになります。
⑥信頼性や根拠のある情報発信
SNSを通じて顧客に対して誠実な姿勢を示すことは、長期的な信頼関係を築くうえで非常に重要です。
これにより、最終的には企業そのもののファンを増やすことにもつながるでしょう。
具体的には、ユーザーからの質問には常に丁寧かつ正確に回答することや、もしも誤った情報を発信してしまった場合はすみやかに謝罪し、訂正を行うことなどが挙げられます。
信頼性のある情報発信を心がけ、根拠に基づいた内容を伝えることで、企業の透明性と誠実さをアピールできます。
⑦知的財産権の保護
コンテンツを作成するときは、第三者の著作権や肖像権、商標権を侵害しないよう、社員全員に周知徹底しておきましょう。
たとえば、他社の画像やイラストを許可なくSNSで投稿することは絶対に避けなければなりません。意図せず写真に映り込んでしまった場合でも、ぼかしを入れたり背景を削除したりするなど、適切な加工を施して対応する必要があります。
少しでも判断に迷うような場合は、公開しないことを強く推奨します。
知的財産権の侵害は、法的な問題に発展するだけでなく、企業の信頼性を大きく損ねる可能性があるため、細心の注意を払いましょう。
⑧誹謗中傷の禁止
誹謗中傷が法的および倫理的にいかに問題であるかを明確に示し、何かを批判するような攻撃的な発言は厳しく禁止しましょう。
なぜなら、誹謗中傷や悪質な発言は、SNS上での炎上に発展する恐れはもちろん、企業の信頼を大きく損ねる可能性があるからです。SNSは情報の拡散性が非常に高く、そのような発言は瞬く間に広がり、取り返しのつかない事態になりかねません。
一方で、企業や社員のアカウントが誹謗中傷を受ける可能性もあるため、誹謗中傷コメントを受け取ったときの対応基準や手順を明確にしておきましょう。
具体的には、必要に応じてコメントの削除やプラットフォームへの通報など、適切な対応を迅速に行える体制を整えておきましょう。これにより、被害の拡大を防ぎ、企業イメージを守ることができます。
⑨ステルスマーケティングの禁止
ステルスマーケティングとは、広告や宣伝であることを消費者に隠して、特定の商品やサービスについて宣伝する行為です。
2023年からは、ステルスマーケティングは景品表示法違反によって規制の対象となりました。
倫理的かつ法的に適切なSNS運用を実現するために、SNS運用に関わるすべての社員に対して、以下のような教育を十分に行っておきましょう。
- ステルスマーケティングの定義
- ステルスメーケティングの具体例
- 法令違反した場合のリスク
企業の信頼や品位を損ねることのないよう、このような法令遵守の徹底は欠かせません。
⑩ユーザーからの問い合わせ先
ユーザーから相談やトラブルの連絡があった際の問い合わせ先を明確にしておきましょう。
具体的には、次のような社内の問い合わせ先をきちんと明記しておきましょう。
- 担当部署名
- 連絡先メールアドレス
- 営業時間など
そうすることで、ユーザーは迷うことなく連絡を取ることができ、円滑なコミュニケーションが可能となります。トラブルが発生した場合でも早期に対応できるため、問題が大きくなるのも防ぎやすくなります。
ユーザーとの良好な関係を維持するためにも、問い合わせ体制の整備は欠かせません。
【4ステップ】SNS運用ルールの作成手順
SNS運用ルールを効果的に作成するためには、次の4ステップを参考にしてみてください。
- 【ステップ1】ルールの目的を設定する
- 【ステップ2】関係部署に確認してもらう
- 【ステップ3】確認内容をもとにブラッシュアップする
- 【ステップ4】ルールを周知・徹底する
これらのステップに沿って進めることで、実効性のあるルールを策定できるでしょう。
では、それぞれ詳しく解説していきます。
【ステップ1】ルールの目的を設定する
SNS運用ルールの作成を始める前に、まず「なぜこのルールが必要なのか?」という目的を明確に設定することが重要です。
漠然とした目的ではなく、具体的に何を達成したいのかを定義することで、ルール策定の方向性が定まるからです。
たとえば、以下のように目的を設定します。
- 「炎上リスクの低減」
- 「ブランドイメージの統一」
- 「社員のSNS利用における意識向上」
目的が明確であれば、その後のルール内容の検討や関係者への説明もスムーズに進むでしょう。
この最初のステップを丁寧に行うことで、形だけのルールではなく、実際に機能するルールを作成できます。
【ステップ2】関係部署に確認してもらう
ルールの原案が作成できたら、次に社内の関係部署に内容を確認してもらいましょう。
SNS運用は広報部だけでなく、法務部や人事部、営業部など、さまざまな部署と関係するからです。
法務部には法的リスクの観点から、人事部には社員の行動規範の観点から確認してもらうことで、多角的な視点を取り入れられます。
関係部署からのフィードバックは、ルールの網羅性や実効性を高めるうえで非常に貴重です。それぞれの部署の専門知識や視点を取り入れることで、より完成度の高いルールが作成できます。
【ステップ3】確認内容をもとにブラッシュアップする
関係部署からのフィードバックを受けたら、その内容をもとにルールの原案をブラッシュアップします。
寄せられた意見や指摘を一つ一つ丁寧に検討し、必要に応じてルールに反映させていきましょう。
この段階では、表現の明確化や具体例の追加、矛盾点の解消など、よりわかりやすく実用的なルールになるよう改善作業を行います。場合によっては、再度関係する部署に確認を依頼し、最終的な合意形成をはかりましょう。
ブラッシュアップを繰り返すことで、社内全体が納得できる、質の高いSNS運用ルールを完成させることができます。
【ステップ4】ルールを周知・徹底する
SNS運用ルールが完成したら、最後にそのルールを社内全体に周知し、徹底することが不可欠です。
どんなに良いルールを作成しても、それが社員に伝わっていなければ意味がありません。
次のように、さまざまな方法でルールを浸透させましょう。
- 社内研修
- 説明会
- 社内ポータルサイトへの掲載
- 定期的なメール配信
ルールを周知するだけでなく、定期的にその遵守状況をモニタリングしましょう。そして、必要に応じて見直しを行うことで、ルールが形骸化するのを防ぎ、実効性を維持できます。
企業のSNS運用ルールは『見直し』・『更新』が肝心!
ご存知のとおり、SNSのトレンドや社会情勢は常に変化しています。
そのため、一度作成したSNS運用ルールも、定期的に見直し、必要に応じて更新していくことが欠かせません。
たとえば、新しいSNSプラットフォームの登場や、炎上事例の傾向の変化など、時代に合わせた柔軟な対応が求められます。ルールを更新せずに放置すると、現状に合わない古い情報になり、実効性が失われてしまう可能性が高まります。
最低でも年に一度は、ルールの内容が現状の運用に適しているか、リスクに対応できているかなどを確認しましょう。また、新たなリスクや課題が発見された際には、すみやかにルールを改定し、関係者に周知徹底しましょう。
これにより、常に最新の状況に対応したSNS運用が可能となり、企業イメージを守りながら効果的な情報発信を継続できるでしょう。
モニタリング体制の構築もおすすめ!
SNS運用ルールの実効性を高めるためには、モニタリング体制の構築も非常におすすめです。
モニタリングとは、自社のSNSアカウントだけでなく、社員個人のSNSアカウントや、自社に関する第三者の投稿などを継続的に監視することです。
これにより、ルール違反や不適切な発言、あるいは炎上の兆候などを早期に発見し、迅速に対応できます。モニタリングを通じて得られた情報は、ルールの見直しや改善に役立てられるメリットも。
具体的には、専用のモニタリングツールを活用したり、担当者が定期的にチェックしたりするなど、具体的な方法を検討しましょう。また、モニタリング作業を外注する方法もあります。
企業のブランドイメージを守るうえで、早期発見・早期対応が肝心なのは言うまでもありません。
まとめ
今回は、企業のSNS運用において必要不可欠なルールについてくわしく解説しました。
SNS運用は、顧客との接点を増やし、ブランドイメージを高めるための強力なツールですが、一方で炎上リスクや情報漏洩といった潜在的な危険も持ち合わせています。
おさらいになりますが、企業のSNS運用に関するルールは、対象者や目的に応じて主に4つの種類に分けられます。
- 公式SNS運用ガイドライン(社内向け)
- ソーシャルメディアガイドライン(社員向け)
- ソーシャルメディアポリシー(社外向け)
- コミュニティガイドライン(ユーザー向け)
企業がSNSの運用ルールを検討する際は、以下の10項目を参考にしてください。
- 基本方針や原則
- SNS運用体制
- 個人の責任範囲
- 機密情報の保護
- 投稿内容のトーン&マナー
- 信頼性や根拠のある情報発信
- 知的財産権の保護
- 誹謗中傷の禁止
- ステルスマーケティングの禁止
- ユーザーからの問い合わせ先
SNS運用のルール作成は、以下の4つの手順で作成していきましょう。
- 【ステップ1】ルールの目的を設定する
- 【ステップ2】関係部署に確認してもらう
- 【ステップ3】確認内容をもとにブラッシュアップする
- 【ステップ4】ルールを周知・徹底する
なお、企業のSNS運用ルールは一度作ったら終わりではありません。常に社会やSNSのトレンドに合わせて見直し、更新していくことが、安全かつ効果的なSNS運用の鍵となります。
適切なルールを設け、継続的に運用を見直すことで、企業のSNS運用はより強固なものとなり、貴社のビジネス成長に大きく貢献することでしょう。 ぜひこの記事を参考に、今すぐSNS運用ルールの見直しや策定に取り組んでみてくださいね。